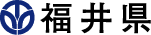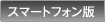身近にある危険(製品事故・誤飲など)に関する事例
・カップ麺容器の変質 ~ 添付以外の油類 加えない ~ (平成31年3月1日掲載)
・歩行型除雪機の使い方 ~ 危険伴う作業 注意必要 ~ (平成31年2月8日掲載)
・湯たんぽの使用 ~ 説明書読み 安全使用を ~ (平成31年1月25日掲載)
・暖房器具の事故 ~ 正しい使用方法 守って ~ (平成30年12月21日掲載)
・草刈り機の事故 ~ 適切な防護服の着用を ~ (平成30年7月13日掲載)
・レインウェア着用の注意点 ~ 自転車 巻き込む事故も ~ (平成30年6月29日掲載)
・マグネットボールの誤飲 ~ 腸壁に穴が開くことも ~ (平成30年6月1日掲載)
・カセットボンベの爆発 ~ 間違った使い方で多発 ~ (平成30年4月27日掲載)
・加熱式たばこ ~ 乳幼児の誤飲に注意 ~ (平成30年3月21日掲載)
・乳児の寝室での事故 ~ ベビーベッドの使用を ~ (平成30年1月24日掲載)
・グリルの乳幼児やけど ~ 使用後も高温 注意して ~ (平成29年11月22日掲載)
・健康食品 思わぬ被害も ~ 異変あれば医療機関へ ~ (平成29年11月8日掲載)
・歯磨き中の事故 ~ 転倒注意 見守って ~ (平成29年10月25日掲載)
・ドライアイスの事故 ~ 触ると危険!取り扱い注意 ~ (平成29年9月27日掲載)
・電化製品によるやけど ~ 乳幼児のいる家庭 要注意 ~ (平成29年7月5日掲載)
・カートからの転落事故 ~ 子どもから目を離さず ~ (平成29年6月28日掲載)
・抱っこひもの事故 ~ 緩みや留め忘れ 必ず確認 ~ (平成29年6月21日掲載)
・加工食品の原材料表示 ~ 未包装の場合、店頭で確認を ~ (平成29年5月24日掲載)
・子どものたばこの誤飲 ~ 直ちに医療機関に受診を ~ (平成29年3月15日掲載)
・2人乗りでスポーク外傷 ~ 幼児座席を必ず使って ~ (平成28年12月21日掲載)
・雨の日の自転車運転 ~ レインウェア原因の事故 ~ (平成28年10月5日掲載)
・スプレー缶の事故 ~ 説明書きの指示守って ~ (平成28年9月7日掲載)
・花火の事故 ~ 6割が10歳未満の子ども ~ (平成28年8月10日掲載)
・薬の誤飲 ~ 包装 1錠ずつにしない ~ (平成28年6月29日掲載)
・耳掃除中の事故 ~ 周囲に注意 安定姿勢で ~ (平成28年6月15日掲載)
カップ麺容器の変質 ~ 添付以外の油類 加えない ~
寒い季節、手軽で温かいカップ麺を食べる機会が増える方も多いのではないでしょうか。
近年n-3系不飽和脂肪酸を含むエゴマ油、亜麻仁油、中鎖脂肪酸を含むココナツオイル(ヤシ油)などが、健康に良い油として紹介されていますが、「この油をカップ麺に入れて食べようとしたところ、容器が溶けてしまった」という事例が報告されています。
独立行政法人農林水産消費安全技術センターなどによる実験結果から、発泡ポリスチレン製容器にエゴマ油や亜麻仁油、ココナツオイルなどを加えて熱湯を注いだ場合、容器の内面が変質して薄くなったり、状況によっては容器の底からお湯がこぼれ出たりする可能性があることがわかりました。カップ麺には、添付の油以外の食用油類は加えないでください。
なお、紙製以外のカップ麺の容器の多くが発泡ポリスチレン製の容器に該当しますが、お湯を注ぐだけでは、このような現象はありません。熱湯によるやけどなどに注意し、容器に記載の調理方法や注意事項をよく読んでお召し上がりください。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成31年3月1日掲載)
歩行型除雪機の使い方 ~ 危険伴う作業 注意必要 ~
積雪が多いこの時期、歩行型除雪機を利用する人も多く、毎年使用中の事故情報が寄せられています。
「緩やかな下り坂をバックしようとしたところ、転倒し、下敷きになり死亡した」「投雪口に詰った雪を取り除こうとして指を骨折した」――。また、作業中の人が事故に遭うだけではなく、「家族が使用中の除雪機にコートが巻き込まれた」など、近くにいた人も被害に遭うことがあります。次のことに注意しましょう。
(1)事前に周囲の建物や足元の障害物の位置を確認する。
(2)除雪機の安全装置が正しく作動しない状態で、絶対に使用しない。
(3)投雪口に詰った雪を取り除く際は、必ずエンジンを停止し、鍵を抜く。
(4)後進時は特に足元や後方に注意し、無理のない速度で使用する。
(5)作業中は周囲に人がいないことを確認し、人を近づけさせない。
寒い雪の中、屋外での作業は滑って転倒するなど、慣れていても危険を伴います。天候や体調の変化に注意し、安全に作業するよう心掛けてください。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成31年2月8日掲載)
湯たんぽの使用 ~ 説明書読み 安全使用を ~
湯たんぽを使う機会が増え、次のような相談が増えています。
(1)電子レンジで温めて使う湯たんぽをオート機能で温めたら、レンジ内で破裂した。
(2)充電式の湯たんぽが充電しても温まらなかったので、充電したまま使用したら湯たんぽが破裂し、やけどをした。
(3)就寝時に湯たんぽを使用したところ、足首が低温やけどになった。
湯たんぽにはお湯を入れて使用するタイプ、電子レンジで温めるもの、電気蓄熱式(充電式)など様々な種類があります。製品によって注意点が異なるため、取扱説明書を読んで、安全に使用しましょう。
(1)身体に長時間接触させないようにしましょう。特に高齢者や子どもは皮膚が薄く、やけどが重症化しやすいです。
(2)製品ごとに指定された加熱方法、加熱時間を守りましょう。
(3)使用前に製品に亀裂や破損がないかを点検しましょう。
また、製品がリコールの対象になっていないかを確認することも大切です。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成31年1月25日掲載)
暖房機器の事故 ~ 正しい使用方法 守って ~
寒い冬には電気ストーブなどの暖房機器はなくてはならないものです。誤った暖房機器の取り扱いが思わぬ事故につながることもあるので、注意しましょう。
【事例1】石油ストーブを消火せずに給油タンクに給油したところ、給油タンクのネジ式のふたの閉め方が不完全だったため、セットしようとした際に漏れた灯油にストーブの火が引火し、火災になった。
【事例2】電気ストーブのそばで寝ていたため、布団がヒーター部に近づいて着火し、火災になった。
いずれの事例も間違った使用方法によって事故が起きています。事故防止のために、次のことを守りましょう。
布団やカーテン、新聞や雑誌などの近くで使用しない▽洗濯物などを暖房機器の上につるして乾かさない▽就寝中は必ず火を消し、外出時は電源プラグをコンセントから抜く▽温風のあたるところにスプレー缶などを設置しない
リコール製品による事故も発生しているため、使用している製品がリコール対象かどうか、情報を確認しましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年12月21日掲載)
草刈り機の事故 ~ 適切な防護具の着用を ~
夏場を迎え、草刈り機を使って草刈りや庭木の手入れをする機会が多くなります。草刈り機は、ホームセンターやインターネットで簡単に購入できるうえ、最近は軽量化され、手軽に使える便利な機械になりました。しかし、鋭利な刈り刃がついており、使用中は高速で回転するため、慎重に取り扱わないと大けがをすることがあります。
「刃がコンクリートにあたり、コンクリートの破片が飛んできて目に傷がつき出血した」「つたが草刈り機の刃に絡み、回転が止まってしまった。つたを取った途端、刃が回転し始め大けがをした」
あらかじめ作業場所を確認して、石などの障害物を取り除きましょう。また、「短時間だから」「着込むと暑いから」との理由で防護具を装着しないまま作業をすると、思わぬ事故につながりかねません。作業時は長袖、長ズボン、保護メガネ、すね当て、手袋、ヘルメットなど適切な防護具を着用しましょう。
周囲の人を巻き込む事故も起きています。作業時は周囲に気を配り、無理な体勢で作業をしないようにしましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年7月13日掲載)
レインウェア着用の注意点 ~ 自転車 巻き込む事故も ~
雨の日にレインウェアを着て自転車に乗る際、「フードで周りが見えず転倒した」「ハンドルにぶら下げていたレインウェアを入れた袋が前輪にからまって転倒し骨折した」といった事故が発生しています。
レインウェアには、上下一体で、コートのように着るレインコート、上着とズボンが分離しているレインスーツ、上下一体で、フードに首を通してかぶるポンチョ、ポンチョの前側の丈が長くなっているロングポンチョなどがあります。
ウェアの裾が前輪や後輪と接触し、巻き込まれる可能性があるので注意しましょう。風が強い場合、ロングポンチョは風にあおられ舞い上がって視界が遮られることがあり、危険です。風が強い日は使用しないようにしましょう。
また、使用前にレインウェアの裾が車輪と接触していないか、フードに視界が遮られていないかを確認しましょう。レインウェアの袋をハンドルにかけて運転しないようにし、前かごに収納袋を入れて運転する場合、収納袋のひもが垂れさがらないように短く束ね、事故を防ぎましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年6月29日掲載)
マグネットボールの誤飲 ~ 腸壁に穴が開くことも ~
幼児が複数のマグネットボールを誤って飲み込んでしまい、腸壁に穴が開いて手術が必要になるという事故が起きています。
マグネットボールは大きさが直径3mmから30mm程度で、玩具として販売されている磁石です。磁力で複数個の磁石をつなぎ、さまざまな形を作って遊ぶことができます。材質はネオジム磁石と表示されているものが多く、磁力がホワイトボードなどに用いられる磁石の10倍以上とされています。
3mmほどの小さいマグネットボールの場合、複数個を同時に誤飲する可能性が高く、腸内を通過できない大きさになる恐れがあります。また、複数個の磁石を異なったタイミングで誤飲した場合には、腸内のそれぞれ別の場所にある磁石同士が引き合って、腸壁を挟んだ状態でとどまり、腸壁に穴が開いてしまう危険性があります。
保護者が気付かないうちに誤飲する可能性もあるので、特に強力な磁力を持つマグネットボールを与えないようにしましょう。万が一誤飲した可能性がある場合は、すぐに医師の診断を受けましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年6月1日掲載)
カセットボンベの爆発 ~ 間違った使い方で多発 ~
カセット式卓上コンロを使う際、手軽に使えることで油断したり、間違った使い方をしたりすることによる事故が多発しています。
カセットコンロに大きな鍋をかけて料理していたところ、カセットボンベが爆発し、やけどをしたという事例がありました。コンロを2台並べて、その上に鉄板を置いて使っていたところ、ボンベが爆発したとの事例もあります。
これらは、大きな鍋や鉄板をコンロに載せたため、放射熱でボンベが加熱されて、ボンベ内の圧力が異常に上昇し、爆発したものと思われます。
ほかにも、ボンベの取り付け不良でガスが漏れ、漏れたガスに引火して爆発した事例や、コンロの五徳をひっくり返したまま使用して爆発したとの事例もあります。また、暖房器具や磁気調理器具の近くなど、高温になる場所に置くことも大変危険ですのでやめましょう。
使用方法や保管方法を間違えると、大きな事故につながります。使用方法などの説明書きを必ず読み、その指示を守るようにしましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年4月27日掲載)
加熱式たばこ ~ 乳幼児の誤飲に注意を ~
ここ数年、たばこ葉に火をつけずに、電気的にヒーターなどで加熱する「加熱式たばこ」という新しいタイプのたばこが販売され、煙やにおい、タールなどの吸入や空間への排出が少ないとされることから、利用者がふえています。
一方で、加熱式たばこの誤飲事故の情報が医療機関ネットワークなどに寄せられています。その多くが乳幼児の事故です。使用前のものを箱から出したり、使用後にゴミ箱に捨てられたものを取り出して口に入れたりする事故が発生しています。
使用前の加熱式たばこには、1本で中毒症状が現れるおそれのある量の二コチンが含まれています。紙巻きたばこと同じく、スティックなどは乳幼児の手の届かない場所に保管しましょう。また、加熱式たばこは火を始末する必要がないので直接ゴミ箱へ捨てることができますが、乳幼児が見えるところや取り出せるところに捨てないようにしましょう。
もし、乳幼児が加熱式たばこのスティックなどを誤飲した場合は、水や牛乳などを飲ませず、直ちに医療機関を受診しましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年3月21日掲載)
乳児の寝室での事故 ~ ベビーベッドの使用を ~
0~1歳児が大人用のベッドから転落し、頭蓋骨を骨折したり、窒息したりする事故が起きています。
2010年12月~2017年6月に医療機関から消費者庁へ寄せられた事故の報告には、6歳以下の子どもがベッドから転落する事故が1,120件ありました。このうち、0~1歳児が大人用ベッドから転落する事故は564件で、うち頭部の受傷(頭蓋内損傷、頭蓋骨骨折、頭部や顔のすり傷、打撲)は400件以上でした。
このような事故を未然に防ぐにはどうすればいいか。首がすわる、寝返りができる、ハイハイができる、つかまり立ちができる、などの運動機能の発達状況を確認し、「まだ動けないはず」という思い込みで大人用のベッドに1人で寝かせることのないようにしましょう。満2歳になるまでは、できるだけベビーベッドを使用し、常に柵を上げて寝かせるようにしてください。
また、寝かしつけのために大人用のベッドで保護者が添い寝する場合は、窒息を防ぐため、子どもの頭や顔が挟まる隙間をなくすなど、寝室の環境には十分注意しましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年1月24日掲載)
グリルの乳幼児やけど ~ 使用後も高温 注意して ~
一般家庭の台所に広く普及しているグリル付きコンロで、1歳前後の子どもが、調理中や使用後のグリル扉などに触り、やけどをしたという事例が寄せられています。
つかまり立ちや伝い歩きなど、行動範囲が広がる時期は、身長とグリルの高さが同じくらいなので簡単に手が届いてしまいます。乳幼児は皮膚が薄く、反応も遅いため、大人よりも低い温度でやけどします。2度以上の手指のやけどが多く、通院が必要な場合もあります。
グリルで魚を焼いた場合、扉の窓中心の温度が150度まで上がることもあり、使用後でも、15分程度は50度以上の状態が続きます。IHクッキングヒーターのグリルにはオーブン機能があり、長時間調理すると、高温抑制扉でも高温になってしまいます。
やけどの危険性については、本体や取り扱い説明書の表示を確認しましょう。調理中はもちろん、使用後であっても、しばらくはグリル窓が高温になっています。子どもを近づけないように注意しましょう。万が一グリルに触れた場合は、すぐにきれいな流水で冷却しましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年11月22日掲載)
健康食品 思わぬ被害も ~異変あれば医療機関へ ~
インターネットなどの通信販売で、スタイルアップやバストアップをうたった健康食品が多く出まわっています。最近では、東南アジア原産の植物「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品を飲んで、嘔吐や腹痛、じんましんなどの症状が出た、女性特有の生理作用に影響が出たといった相談が寄せられ、国の機関も注意が必要だと警鐘を鳴らしています。
「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品には、強い女性ホルモンと同様の作用を持つ成分が含まれるとされています。山地や収穫時期、樹齢などによって含有量に幅があり、現時点では安全な接種量についてよく分かっていないため、思わぬ健康被害が発生する恐れがあります。
「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品を摂取して体に異変を感じたら、直ちに接種をやめて、医療機関を受診しましょう。
また健康食品を購入する際、定期購入になっていることに気が付かず、健康被害が起きても解約できない事例が多発しています。必ず、利用規約を確認するよう心がけましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年11月8日掲載)
歯磨き中の事故 ~ 転倒注意 見守って ~
歯磨きは、虫歯予防や口の中の衛生のための大切な生活習慣です。子どもにとっても毎日の習慣ですが、その一方、歯ブラシをくわえたまま転倒してのどを突くなど、歯磨き中の事故が多く発生しています。
「1歳の子どもが歯ブラシを口にくわえてソファに座っていたが、前のめりに転倒し、のどに刺さった」「4歳の子どもが歯ブラシをくわえながら走って転倒し、のどに突き刺さって口の奥から出血した」という事故が報告されています。
特に事故が多いのは1歳から3歳です。自分で歯磨きをさせるときは、次のことに気をつけましょう。
(1)歯磨き中は保護者がそばで見守り、床などの安定した場所に座らせる。
(2)歯ブラシを口に入れたり、手に持ったりしたまま歩かせないようにする。
(3)歯ブラシは、のど突きカバーなど安全対策が施されたものを選ぶ。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年10月25日掲載)
ドライアイスの事故 ~ 触ると危険! 取り扱い注意 ~
「スーパーでアイスクリームを購入し、ドライアイスを入れて持ち帰ったところ、子どものひじが袋に触れていたようで、やけどのような症状になった」「ドライアイスをポリ袋に入れて持ち帰ったら破裂した」という事故が起きています。
ドライアイスはマイナス78.5度と非常に低温です。素手で触ると急激に冷やされて血行不全に陥り、さらに接触を続けると凍傷を引き起こします。軽度の場合は局部的に赤くなって痛み、中度の場合は水泡ができ、重度の場合は損傷が皮下組織にまで及び、危険性の高いものです。
子どもにとっては、空気に触れると白い煙が出るドライアイスは興味深いものです。素手で触ったり、口に入れたりしないように、十分注意してください。
また、ドライアイスは空気中ですぐに気化し、そのときの体積が約750倍に膨張します。密閉した容器に入れると、破裂などの事故を引き起こす恐れがあるので、ペットボトルや瓶など、密閉容器には絶対に入れないでください。
事故にあわないよう、注意点を守って安全に取り扱い、ドライアイスが余ったら、風通しのよい場所で自然に消滅させましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年9月27日掲載)
電化製品によるやけど ~ 乳幼児のいる家庭 要注意 ~
ポットや炊飯器などの電化製品によって、乳幼児がやけどする事故が多発しています。
消費者庁によると、今年3月までの6年間に、電気ポット・ケトルで130人以上、炊飯器で100人以上の乳幼児がやけどを負ったとの報告があります。乳幼児のいる家庭で、手の届く高さや動き回る範囲に製品やコードを配置すると、事故が起きやすくなり、注意が必要です。
子どもは時として予想外の行動をとります。昨日までは手の届かなかった場所でも、次の日には触れるようになっているかもしれません。製品の本体だけではなく、コードも含めて子どもの手の届かない場所に置くことが重要です。
電化製品を購入する際、第三者認証機関によって、製品試験や品質管理が調査された証である「Sマーク」の付いている製品をお薦めします。また、炊飯器であれば、「蒸気レス」などと排出の抑制をうたう製品、電気ポット・ケトルであれば、転倒時に水が流れないなど、安全機能のある製品も有効でしょう。
もし、広範囲にわたってやけどした場合は、無理に服を脱がすことなく、シャワーなどで冷やし、ぬれたバスタオルで体を包んで、すぐに医療機関を受診するようにしましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年7月5日掲載)
カートからの転落事故 ~ 子どもから目を離さず ~
ショッピングセンターなどにある荷物を運ぶための店舗用カートから、子どもが転落、転倒する事故が起きています。
「買い物に行き、高さ1mくらいのカートの幼児用座席に子どもを乗せていたところ、目を離したすきにカート上で立ち上がって商品に手を伸ばそうとして転倒し、頭部を打ち付けた」「子どもがよじ登ろうとしてカートごと転倒し、おでこを切った」というものです。
カートからの転落、転倒などの事故では、頭部への危害が目立ちます。店舗の床はコンクリートのように硬いため、子どもがカートに立つと、より高い場所から転落して頭部を打ち付けることになり、危険性が高まります。すり傷や打撲だけでは済まず、頭蓋内損傷を負ったという事例もあります。
子どもをカートに乗せているときは、絶対に目を離さず、子どもが立ち上がらないよう注意し、ベルトなどがあればしっかりと装着しましょう。幼児用座席のないカートには、子どもを乗せてはいけません。カート置き場の表示や本体の注意事項をよく確認して正しく利用し、事故を防ぎましょう 。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年6月28日掲載)
抱っこひもの事故 ~ 緩みや留め忘れ 必ず確認 ~
子どもを連れての外出に便利な抱っこひもですが、乳幼児が抱っこひもから転落した事故の情報が、消費者庁に寄せられています。
「抱っこひもを使って子どもを抱っこしたが、親の背中の後ろにある抱っこひものバックル(ベルトの留め具)がきちんとはめられていなかったために、肩のベルトがずれて子どもが地面に転落し、骨折した」「抱っこひもで子どもを抱っこしたまま前かがみになった時に、肩ベルトと脇のひもの間から子どもが転落して額を打った」といった事故です。
赤ちゃんの転落は、重傷事故につながるおそれがあり、大変危険です。万が一子どもが転落した場合は、異変がなくても医療機関を受診しましょう。
抱っこひもで抱っこしたまま前にかがむ時は必ず子どもを手で支え、物を拾う時、おんぶや抱っこをする時、下ろす時はひざを曲げて低い姿勢でするようにしましょう。
取扱説明書の使用上の注意点を確認し、実際に使う際には、ひもの緩みやバックル類の留め忘れがないかなどを必ず確認してください。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年6月21日掲載)
加工食品の原材料表示 ~ 未包装の場合、店頭で確認を ~
「洋菓子店で購入したケーキを食べたら洋酒が使われていたが、原材料名の表示がなかったので食べるまでわからなかった。子どもに与えていたら健康被害があったかもしれない」という相談がありました。
食品表示法は、消費者に販売する加工食品のうち、パックや缶、袋などの包装されているものについて、原材料名などの表示を義務づけています。相談のような包装されていないものには、原材料名の表示義務はありません。店頭で確認するようにしましょう。アルコールが入っていることを知らずに菓子類や飲み物を与えてしまい、子どもの具合が悪くなったという報告もあります。
事例(1)ブランデーが使われたパウンドケーキを食べて、7歳の子が嘔吐した。
事例(2)3歳の子がお土産でもらったゼリーを食べると、顔が赤くなり、酒臭くなって酔っぱらったような状態になった。
事例(3)祖母が低アルコール飲料をジュースと間違えて1歳の孫に飲ませてしまい、中毒症になった。
子どもの場合、アルコールの摂取量によっては深刻な事故につながるおそれがあります。表示や店頭で確認するなど、日頃から注意しましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年5月24日掲載)
子どものたばこの誤飲 ~ 直ちに医療機関に受診を ~
厚生労働省から、2015年度の小児の誤飲事故について発表がありました。1年間に286件の誤飲事故が発生し、そのうちのトップはたばこで63件、次いで医薬品・医薬部外品が48件、プラスチック製品が40件と続きます。
たばこは毎年度、誤飲事故の上位にあります。誤飲した年齢はつかまり立ちやハイハイを始めた6~11か月の乳児、両手で容器を持ち上げられる1歳~1歳半の幼児に集中しています。
事故の内容は、未服用のたばこや吸い殻を食べたり、たばこの吸い殻が入った空き缶やペットボトルの液を飲んだりしてしまったというものです。
たばこに含まれるニコチンは猛毒です。特にたばこの浸出液はニコチンが体に吸収されやすい状態になり子どもが飲み物と間違えて飲むと症状が悪化する危険があります。症状が軽い場合は、悪心や嘔吐、重くなるにつれ顔色不良、チアノーゼが生じます。誤飲した現場を家族が目撃していないことも多く、小児は正確な自己申告もできません。
誤飲を防ぐために、たばこや灰皿を子どもの手の届く場所に置かないようにしましょう。もしたばこを誤飲した場合は、直ちに医療機関で受診しましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年3月15日掲載)
2人乗りでスポーク外傷 ~ 幼児座席を必ず使って ~
自転車の2人乗りをしていて、後ろの同乗者の足が後車輪に巻き込まれてけがをする「スポーク外傷」を伴う事故が多く発生しています。スポークとは車輪の中心部から車輪の枠に放射状にのびる針金状の部品です。回転中の車輪のスポークに巻き込まれて負うけがを「スポーク外傷」と呼びます。
医療機関ネットワークによると、スポーク外傷の事例が過去5年間で172件報告されています。自転車に同乗した6歳未満の子どもがけがをした事例は半数以上の90件もあり、スポーク外傷は子どもに多く、大きなけがを負う可能性があるといえます。
幼児座席を使用せずに、子どもが直接荷台に座ってけがを負うケースのほかに、幼児座席を使用していても、子どもがはしゃいで足乗せに足を置いていなかったり、足乗せが壊れていたりしたために発生した事例が報告されています。
6歳未満の子どもを自転車に乗せるときは、足の巻き込み防止のために必ず幼児座席を使用しましょう。また、幼児座席を使用しないで荷台に6歳未満の子どもを座らせるのは道路交通法違反になるのでやめましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成28年12月21日掲載)
雨の日の自転車運転 ~ レインウェア原因の事故 ~
昨年6月1日に施行された改正道路交通法により、自転車の傘差し運転など、危険な運転に対する罰則規定が厳しくなりました。そのため、レインウェアを着用して運転する人が増えました。しかし、次のような事故も発生しています。
(1)レインウェアを来て自転車で走行中、フードで周りが見えず、自動車にはねられた。
(2)走行中、ハンドルにぶら下げていた雨がっぱの収納袋が前輪にからまって転倒し、骨折した。
雨の日には、フードの調節機能を正しく使用しましょう。また、収納袋を前かごに入れて運転する場合、収納袋のひもが垂れ下がらないよう、束ねるようにしましょう。
フードに首を通してかぶるポンチョタイプの場合、前かごや荷台がない自転車では裾がタイヤと接触し、巻き込まれる危険があります。風が強い日には、前かごで覆うよう前丈が長くつくられているロングポンチョでは、風にあおられ舞い上がったときに視界が遮られるおそれもあります。
使用前にレインウェアと自転車の駆動部が接触していないか確認し、風の強い日にはロングポンチョタイプは使用しないようにし、事故を防ぎましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成28年10月5日掲載)
スプレー缶の事故 ~ 説明書きの指示守って ~
殺虫剤、ヘアスプレー、制汗消臭剤など、スプレー缶は日常生活の様々なところで使われています。しかし、スプレー缶の事故も多く発生しています。
例えば、自動車の車内に芳香剤のスプレー缶を置いていたところ、スプレー缶が破裂し、フロントガラスが破損。さらに、天井にも傷がついたという事故があります。炎天下の直射日光で車内の温度が高くなり、缶の内部の圧力が上がったことが原因と思われます。
スプレー缶には、高温になると破裂の危険性があることが書かれていました。炎天下に駐車した車内の温度は60度にもなると言われています。車内にスプレー缶などを放置しないようにしましょう。
他にも「筋肉痛用のスプレーをサポーターの上から噴射した。しばらくしてたばこを吸ったところ、サポーターに火がついた」「制汗消臭剤を両手の甲につけたら皮膚が紫色になり、病院で凍傷と言われた」といった事故もあります。
使用方法や保管方法を間違えると思わぬ事故につながる危険性があります。商品の説明書きは必ず読み、その指示を守るようにしましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成28年9月7日掲載)
花火の事故 ~ 6割が10歳未満の子ども ~
夏の夜に、大人も子どもも手軽に楽しむことが出来る花火。一方で、花火による事故の報告も毎年多数寄せられています。
【事例1】子どもと線香花火をしていたところ、火の玉がサンダルを履いた子どもの足の甲に落ち、やけどした。
【事例2】手持ち花火で子どもが遊んでいたところ、急に振り向き、近くにいた子どもの足に火花がかかった。
【事例3】打ち上げ花火に点火したが火が付かなかったので、のぞきこんだら突然噴出した。
花火の事故で最も多いのがやけどで、特に10歳未満の子どもの事故が全体の6割を占めています。
花火は、火薬や火を使う危険と隣り合わせの遊びです。また、子どもは大人が予想しない動きをすることもあります。安全に花火を楽しむために、必ず大人が付き添い、花火のパッケージや本体に記載されている注意事項を読んでから始めましょう。
火が移りやすい素材の服や、肌の露出の多いサンダルなどの靴は避けましょう。着火用のろうそくなどによる着衣への着火事故も起きています。浴衣や長いスカートを身につけているときは、袖や裾が火に触れないように気をつけましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成28年8月10日掲載)
薬の誤飲 ~ 包装 1錠ずつにしない ~
高齢者が食品以外の物を誤って飲んだり、食べたりしたという事故情報が寄せられています。特に多いのが、薬をPTP包装シート(プラスチックにアルミなどを貼り合わせたもの)ごと飲んでしまうというものです。次のような事例がありました。
事例1 朝食後、家族が切り取って渡した内服薬をPTP包装シートごと飲み込んだ。のどにつかえた感じがあり、病院を受診。食道にPTP包装シートがあることがわかったので胃カメラで回収してもらった。
事例2 夕食後、内服薬をPTP包装シートごと飲み込んだ。飲み込む時にのどに違和感があり、病院を受診した。食道にあったPTP包装シートを内視鏡で除去。その後、経過観察で入院した。
PTP包装シートを飲み込むと、のどや食道、腸などを傷つける恐れがあります。また、傷みなどの症状が表れるまで誤飲に気付きにくく、検査してもPTP包装シートの素材はX線を透過するため、発見が遅れてしまうこともあります。
PTP包装シートを切って1錠ずつにすると、誤飲しやすいサイズになり、また、切った角が鋭くなって危険です。包装シートは1錠ずつに切り離さないようにしましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成28年6月29日掲載)
耳掃除中の事故 ~ 周囲に注意 安定姿勢で ~
全国の消費生活センターに、耳掃除でけがをしたという事故情報が多数寄せられています。「耳掃除中に子どもがぶつかり、聴力低下を感じて病院へ行った」「子どもの耳掃除で、子どもが動いて耳かき棒が奥に入ってしまい出血した」などというものです。
耳掃除の事故で最も多いのは、自分で耳掃除をしているときに、子どもやペットがぶつかってきてけがをしたというものです。耳掃除は周囲の状況に注意し、安定した姿勢、場所でするようにしましょう。
子どもの耳掃除をするときは、動いたらけがをするおそれがあることを理解させましょう。動いてしまう可能性があるときは、無理に耳掃除をしないほうがよいでしょう。
また、乳幼児が大人のまねをして自分で耳掃除をしたり、遊びで耳掃除をしていてけがをしたりするケースもあります。綿棒でも大きなけがを負う場合があるので、耳かき棒や綿棒を乳幼児の手の届く場所に置かないようにしましょう。
本来、外耳道には耳あかを外へと押し出す作用があるので、耳掃除の基本は外まで運ばれた耳あかを取るだけで良いと言われています。耳かき棒や綿棒を奥に入れすぎないように注意しましょう。
(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成28年6月15日掲載)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、syouhi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
消費生活センター
電話番号:0776-22-1102 | ファックス:0776-22-8190 | メール:syouhi-c@pref.fukui.lg.jp
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階 相談受付:9:00-17:00(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)